子どもの教育資金の準備には計画が欠かせない。学資保険はその有力な選択肢である。
本記事では、学資保険の仕組みやメリット、利率(いわゆる返戻率)、デメリットをFPの視点からわかりやすく解説する。賢い選択のために必要なポイントも紹介する。
- 学資保険の基本的な仕組みと特徴
- 利率(返戻率)を含むメリットとデメリット
- 自分に合った学資保険の見極め方
学資保険とは?
学資保険とは、子どもの教育資金を計画的に準備できる貯蓄型生命保険である。
契約者が毎月一定の保険料を支払うことで、子どもの進学などの節目に祝い金や満期保険金を受け取れる仕組みだ。さらに、契約者に万が一があった場合は、以降の保険料の支払いが免除される。
返戻率と呼ばれる指標でおおよその利率が把握できることも特徴の一つである。
学資保険のメリット
学資保険には、教育資金を無理なく準備できるなど、いくつかのメリットが存在する。具体的に主な利点を挙げてみよう。
計画的に教育資金を準備できる
学資保険は決まった月額保険料を支払うため、計画的に貯蓄が進む。これにより、教育資金の準備に失敗しにくい。
契約者に万が一の際に保険料の払込みを免除できる
契約者が死亡または高度障害状態になった場合、その後の保険料払込みが免除され、満期金が保障される。これにより、家計が困窮しても教育資金の受け取りが確保される。
税制優遇を受けられる
学資保険の保険料は、生命保険料控除の対象となるため、所得税や住民税の軽減メリットを享受できる。
受取時期や方法を柔軟に選べる
祝い金の受け取り時期や方法は商品により異なるが、分割受取りや一括受取りが選択可能であり、資金の使い方に応じて柔軟に対応できる。
学資保険の利率(返戻率)とは?
学資保険の「利率」として多くの人が気にするのは、返戻率である。これは支払った保険料に対してどれだけの金額が戻ってくるかを示す割合だ。ここでは返戻率の基本的な知識と計算方法、高めるポイントを簡潔にまとめる。
返戻率の基礎知識
返戻率は、満期時に受け取る金額を総払込保険料で割り、百分率で表す。例えば返戻率105%なら、支払った保険料より5%多く戻ってくる意味を持つ。
返戻率の計算方法
返戻率は「満期保険金総額 ÷ 払込保険料総額 × 100(%)」で算出される。保険料の払込期間や保障内容によって返戻率は変動する。
返戻率を高めるポイント
返戻率は、払込期間の短縮や一括払いを選択する、保障内容の見直しなどで高めることが可能。ただし、家計への負担との兼ね合いを考慮すべきである。
学資保険のデメリット
学資保険にはメリットがある一方で注意すべき点もある。主なデメリットについて説明する。
返戻率が低めのことが多い
市場の低金利環境から、学資保険の返戻率は他の金融商品に比べて低めに設定されるケースが多い。利率だけに期待しすぎてはいけない。
途中解約すると元本割れリスクがある
早期解約すると払込額より少ない返戻金となり、元本割れのリスクがある。よって契約前に資金が固定される点を理解することが重要である。
資金の流動性が低い
学資保険は解約しなければ資金を引き出せず、急な出費に対応しづらい。緊急時資金は別途準備することが望ましい。
教育プランの変更に対応しづらい
子どもの進路変更や教育費の増減などプランの変化に柔軟に対応しにくいので、家計の変化に合わせて見直しも検討すべきである。
学資保険が向いている人・向いていない人
学資保険が誰にでも適しているわけではない。向いている人と向いていない人の特徴を紹介し、賢い選択の参考にしてほしい。
学資保険が向いている人の特徴
安定的に計画を立てて教育資金を積み立てたい人や、将来のリスクに備えたい人に向いている。
学資保険が向いていない人の特徴
すでに教育資金が十分に確保できている人や、資産運用で効率よく増やしたい人、自由に資金を使いたい人には向かない。
他の資金準備方法との組み合わせ方
預金や投資信託、NISAなど他の方法と組み合わせることで、リスク分散と効率的な資金準備が可能になる。
学資保険を賢く活用するために
学資保険は、子どもの教育費を計画的に準備する上で優れた手段であるが、返戻率やデメリットもしっかり理解することが重要だ。自分の生活状況に合った商品を選ぶためにも、多角的な情報収集と専門家の相談を活用しよう。
- 学資保険は教育資金の確実な準備に役立つ
- 返戻率の高さだけでなくメリットとデメリットを総合的に判断することが必要
- 見直しや組み合わせでリスクヘッジも重要である
- 向いている人・向いていない人を見極めることが大切
- 専門家のアドバイスを活用して納得のいく選択を

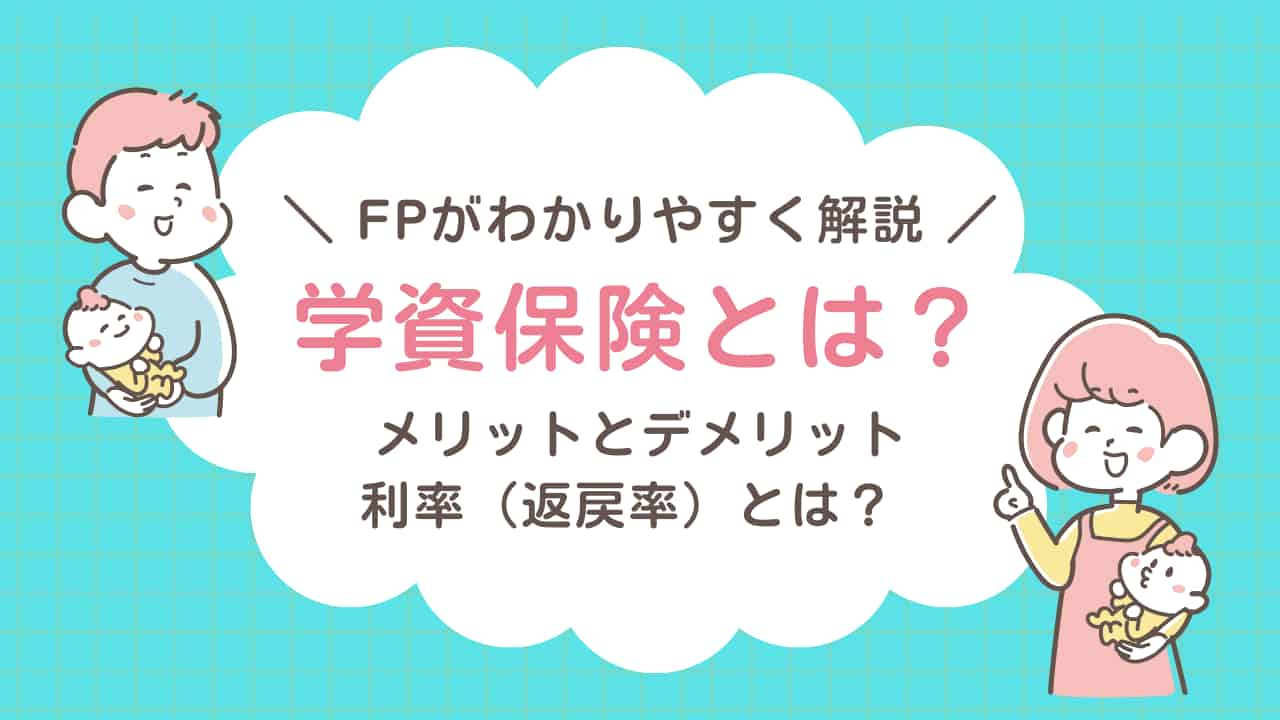
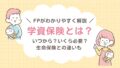

コメント